今回は、「居酒屋のような特に夜のディナータイムの営業がメインとなる店舗で、ランチサービスをどのように位置づけるか」というテーマを論じたいと思います。
(1)ランチサービスの目的は?
居酒屋や料理店等、夜のディナータイムの営業がメインとなる店舗において、ランチサービスを行うのは色々な理由があると思います。多くの店舗では前日の営業で使用した食材が余ってしまうので、それを廃棄するとロスが発生することになるし、SDGsの観点からも時代に合わないということをよく伺います。そのため、その食材を活用して数百円から二千円程度といった比較的抑えた価格でランチサービスを提供している店舗は多いです。
私が今回ランチサービスについて論じたいと考えたのは、ある店主から聞いた話がきっかけでした。その店は料理の評判も良く、ランチサービスも好評でしたが、昼の売上は全体から見れば限定的。夜の仕込み時間も確保しにくくなることから、ランチ営業をやめる決断をしたそうです。
店主と奥様の2人で経営しているワンオペに近い形の店舗のため、業務での疲労の軽減も図りたいということでした。
(2)食材ロスによる損失回避を、ランチサービスで目論む
色々なお店の店主に話を伺うと、ランチサービスは食材ロスによる損失を避けるために、原価が確保されていればそれで良いという消極的な意見が多くあります。確かに、日持ちのしない食材を購入して夜のお客様に提供しても、材料が残ってしまうとその夜で稼いだ粗利部分が食材ロスで消えてしまう可能性があります。従って、食材ロスになるような材料を、原価ベースでも良いのでランチサービスで提供することは、在庫処分損を避ける意味で効果があります。
また、お店には賃借料や設備の償却費といった固定費がかかるので、店舗を運営する時間を出来るだけ長くしてお客様が利用する稼働時間を増やすことは、採算を向上させるうえで合理性があります。
一方で、ランチサービスの準備が必要になると、店舗で働く人たちの労働時間は長くなり、肉体的疲労も大きくなります。特に夏場は高温であるし、火を使うキッチンにいる時間が長くなると体力が急激に消耗します。ランチサービスには、良い面とそうではない面の両方があります。
(3)ランチサービスを店舗プロモーションの手段として考える
色々な考え方がある中で、ランチサービスはお客様に主力である夜の来訪をしてもらう宣伝効果があり、これがランチサービスを行う一番の目的であると考える店主もいます。最近の店舗の宣伝は、インスタグラムやLINEを用いて積極的に行っているお店も多いです。しかし、店舗に興味を持ったお客様、つまり店舗を認知したお客様が、単価が高くなるディナーサービスにいきなり来店するのはハードルが高い、と指摘する店主もいらっしゃいます。
この指摘は、以前このコラムで説明した、お客様が常連客になるプロセスにも通じます。店舗を認知して来店への興味を持った場合において、ランチサービスは、比較的抵抗なく初めて来訪する機会となります。
ランチサービスをきっかけに来店してもらい、ディナーサービスで提供されるメニューと価格に納得してもらい、店を気に入って常連客になるというプロセスを踏むお客様の数は少なくないという主張です。ランチサービスの意義を認識している飲食店においては、この効果を実感されているようです。
(4)ランチサービスは、新規顧客を得る絶好の手段ではないか?
ランチサービスにどのくらい力を入れて営業するかは、お店の規模や立地などによっても方針が変わってくると思います。一方で、固定客を増やしたいと思っているお店にとって、店舗認知プロモーションの有効な手段と言えそうです。
つまり、食材ロス回避という防衛的なランチサービスだけでなく、店舗認知を促進させるための意欲的なランチサービスの提供が存在しています。もちろん店舗の持続が最も重要なので、店主の体力や時間効率を考えて検討することが肝要です。ランチサービスが持つ大きな2つの目的を考えて、バランスを取った経営をされてみては如何かなと思いました。
本コラムが皆様の参考になれば幸甚です。
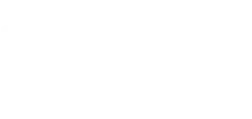
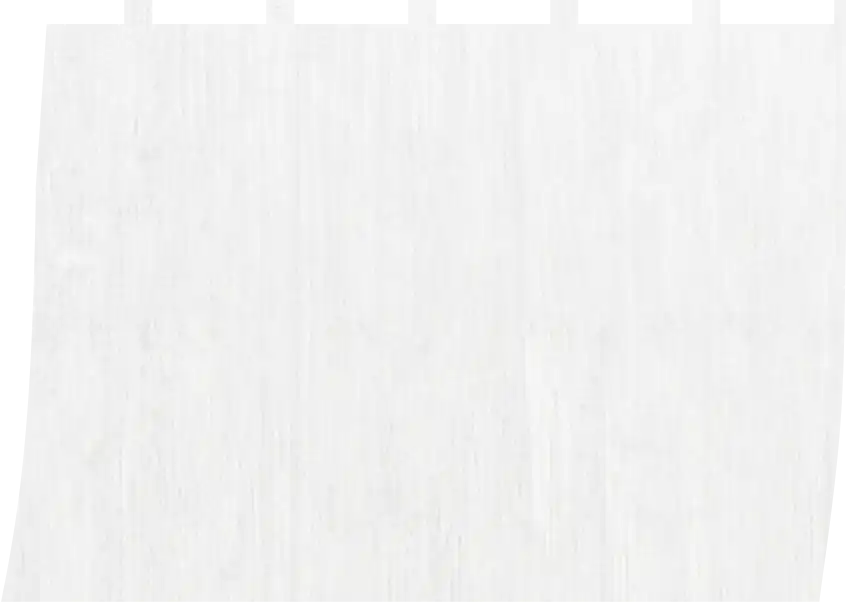
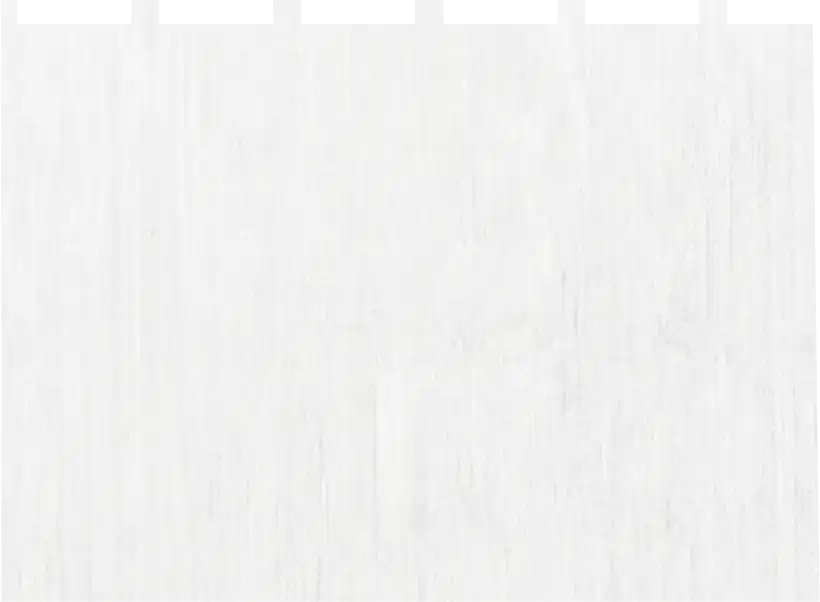

 あきない活性化コーディネーター
あきない活性化コーディネーター